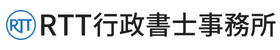相続放棄をするには
私は叔父が亡くなった時に相続放棄をしたことがあります。その時は父親の代襲相続でしたが、いろいろと複雑な事情があったため相続放棄を選択しました。
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がないという意思を、法律にのっとって家庭裁判所に申述する手続きです。プラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も一切受け継がなくなります。
1.相続放棄ができる期間
相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った日から「3か月以内」です。この期間を「熟慮期間」と呼びます。たとえば、亡くなった事実を後から知った場合は、その知った日から3か月以内ということになります。
期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。例外的に期間延長や特別な事情がある場合は、裁判所の判断に委ねられます。
2.相続放棄の申請先
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行います。最寄りの裁判所ではなく、必ず被相続人の住所地の管轄となる点に注意が必要です。
3.必要書類
相続放棄には、以下のような書類が必要になります。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式に記入)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのつながったもの)
- 申述人(放棄をする人)の戸籍謄本
- その他、必要に応じて住民票や関係書類
家庭裁判所によっては、追加書類の提出を求められることがあります。事前にホームページなどで確認すると安心です。
4.手続きの流れ
まず、被相続人が死亡したことを確認し、自分が相続人であることを把握します。次に、相続財産(不動産、預金、借金など)を調査し、放棄すべきかどうかを判断します。
その上で、家庭裁判所に必要書類を提出します。審査の過程で、裁判所から問い合わせや補正の連絡がくることがありますが、通常は1~2か月程度で「相続放棄申述受理通知書」が届き、正式に放棄が認められます。
5.注意点
一度相続放棄が受理されると、原則として取り消すことはできません。放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
また、放棄したことで次順位の相続人(たとえば兄弟や甥・姪)に相続権が移るため、家族内での理解や話し合いも大切です。
さらに、「遺産はもらわない」と家族間で口約束しただけでは法的な放棄とはなりません。必ず裁判所で正式な手続きを行う必要があります。
まとめ
相続放棄の手続きは、期限や書類の不備により却下されるケースもあります。行政書士などの専門家に依頼することで、正確かつスムーズな手続きを進めることができます。
相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。