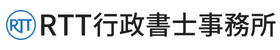遺言書が必要な7つの事例 〜今回は「相続関係が複雑」なケース〜
相続関係が複雑な場合
家族構成が複雑な場合、相続でもめごとが起こりやすくなります。
たとえば再婚して前妻との子どもがいる場合や、親族同士の関係が疎遠な場合などは、法定相続分だけでは納得されにくく、トラブルの火種になります。
このようなケースでは、遺言書を作成しておくことが円満な相続の第一歩です。
1. 再婚・前婚の子どもがいる場合
前婚の子どもも法定相続人に含まれるため、遺言がないと想定外の人に財産が分散されることがあります。
遺言書があれば、どの子にどの財産を渡すかを明確に指定できます。
2. 親族間の不仲・疎遠な関係
相続人の中に疎遠な親族がいる場合、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での調停に発展することもあります。
遺言書があれば、相続人の指定や遺留分に配慮した形で早期にトラブルを回避できます。
3. 事実婚・内縁関係がある場合
法律上の婚姻関係がないと相続権は認められません。
しかし、遺言書によって内縁のパートナーに財産を残すことは可能です。
4. 養子・認知した子どもがいる場合
認知や養子縁組の有無によって相続権が異なります。
誤解や争いを避けるためにも、遺言で自分の意向をきちんと残しておくことが大切です。
5. 相続人が多い・関係が複雑
相続人が多いと協議が難航することが多く、感情的な対立や手続きの長期化につながります。
遺言書で役割分担や財産の配分を明示しておけば、スムーズな相続が可能です。
6. 認知症や判断能力が不安な相続人がいる場合
判断能力に問題のある相続人がいる場合、手続きに後見人の選任などが必要となり、時間や費用が大きくかかります。
遺言書があれば、複雑な調整を事前に避けることができます。
7. 紛争を未然に防ぎたい場合
家族間の事情は外からは見えづらいため、第三者にとっては想定外のトラブルが起こりがちです。
遺言書を残しておけば、誰にどのように財産を残すかを明確にでき、誤解や争いを回避できます。
まとめ
家族関係が複雑な方にとって、遺言書は“想い”と“配慮”を形にする唯一の手段です。
自分の意志を明確に残すことで、残される家族に安心と納得をもたらすことができます。
相続・遺言についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
📞 電話:03-6657-5593
📠 FAX:03-6657-4858
📩 メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。