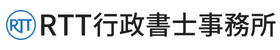飲食店営業許可申請の手順(個人事業主の場合)
私の実家は『大衆酒場』と『スナック』を経営しておりました。私自身は大学卒業後会社員となりましたが、大学時代には手伝うために「食品衛生責任者」の資格、のちに「調理師」免許をとりました。行政書士となった今では飲食店許可や深夜種類提供の届出などの申請業務をメインに行いたいと考えています。
今回は飲食店営業許可申請の手順をご紹介いたします。
1.事前準備(物件の選定・確認)
- 飲食店として使用予定の物件が、飲食営業に適しているか確認します。
- 用途地域の確認(店舗として利用可能か)、排水・換気・手洗い設備の確認などが必要です。
- 図面が必要になるため、物件契約前に保健所に相談すると安心です。
2.食品衛生責任者の設置
- 飲食店には必ず「食品衛生責任者」を1名以上置く必要があります。
- 調理師や栄養士の資格がある場合は自動的に就任できますが、資格がない場合は「食品衛生責任者養成講習会」を受講します(東京都1日講習、12,000円)。
3.店舗の設計・改装
- 保健所の定める基準を満たす必要があります(例:床・壁の素材、手洗い器の数、冷蔵庫の設置など)。
- 改装工事後に再度確認があるため、基準を満たした設計にすることが重要です。
4.事前相談・図面確認(推奨)
- 着工前に保健所へ「設計図」「設備図面」などを持参し、事前に確認を受けることで後のトラブルを防げます。
5.営業許可申請(営業開始の10日前までに)
保健所にて「飲食店営業許可申請書」を提出します。
提出書類の一例:
・営業許可申請書
・施設の構造・設備の図面
・食品衛生責任者の資格証明書
・使用水の水質検査成績書(井戸水使用時)
・賃貸契約書の写しなど
・新規手数料 18,300円(墨田区) 区によって違います。
6.施設検査(立入検査)
- 保健所の職員が実際に店舗に立ち入り、設備・衛生状態の確認を行います。
- 問題がなければ、数日〜1週間程度で許可が下ります。
7.営業許可証の交付
- 許可証の交付後、営業が可能となります。
- 有効期間は原則5年。更新には再度申請が必要です。
8.営業開始・その他届出
- 税務署、都道府県税事務所、市区町村への開業届出なども忘れずに行います。
- 深夜営業、酒類提供、音楽演奏などがある場合は別途の許可(風営法・酒類販売・著作権など)が必要なこともあります。
まとめ
初めて申請する方はもちろん、更新時にも書類の作成や手続きが必要となります。行政書士などの専門家にお任せいただければスムーズに申請することが可能です。
飲食店営業許可についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。